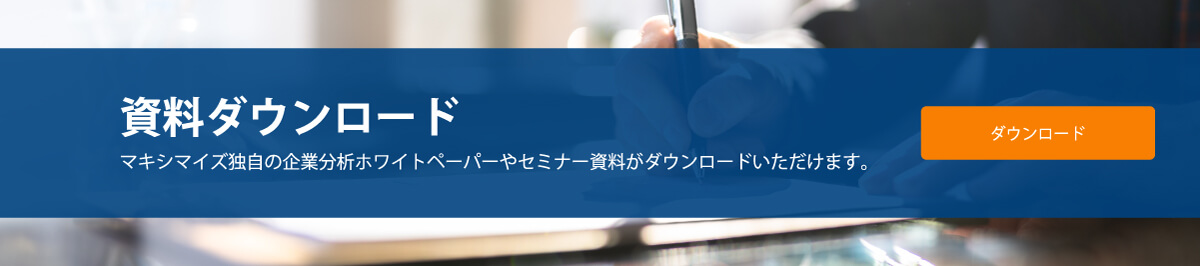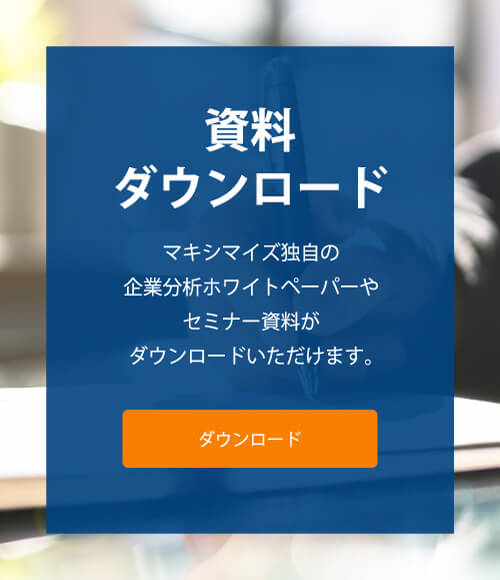「ISO規格がイノベーション管理において不十分な理由("Why ISO Standards Fall Short in Innovation Management")
みなさんこんにちは。マキシマイズの渡邊です。今回も書籍『イノベーションの攻略書(原題:The Corporate Startup)』、『イノベーション・アカウンティング(原題:The Innovation Accounting)』の著者であるダントマ氏のブログ記事をご紹介します。
今回は、「ISO規格がイノベーション管理において不十分な理由("Why ISO Standards Fall Short in Innovation Management")」という、イノベーションマネジメントにおけるISO規格の有用性についてのお話です。では本文をお楽しみください。
「ISO規格がイノベーション管理において不十分な理由("Why ISO Standards Fall Short in Innovation Management")
2024年3月18日
ダン・トマ氏
ISO規格がイノベーション管理において不十分な理由(ダン・トマ氏が"OUTCOME社ウェブサイト"に掲載したブログ記事を、本人の許可を得て翻訳、掲載しています)

現代社会において、長期的な戦略目標においてイノベーションの重要性を認識する企業が増えている。そうした企業の中には、過去にイノベーションによって優れた成果を上げた経験を持ち、その取り組みをさらに強化し、実践を体系化・専門化しようとする企業もあれば、競合他社がイノベーション主導の成長を遂げた成功例に刺激され、自社でもイノベーションに取り組もうとする企業も存在する。
「なぜ」イノベーションに取りくむのかという動機に関わらず、ほとんどの企業が苦労しているのは「どのように実行するか」である。こうした状況の中で、業界標準を指針として参考にする企業も存在する。しかし、詳しく見てみると、イノベーション・マネジメントに関するISO 56000規格群には、企業がイノベーションへの投資から真の成果を得る上で限界がある。
1. 現代の標準規格は昔の標準規格から変わってしまった
標準化の取り組みは、主に製造業によって推進され、とりわけ第二次世界大戦の壊滅的な影響を受けた後にその動きが加速した。標準規格の大半は、特定の素材部品、性質、用途などに焦点を当てていた。それらは客観的かつ無機質であり、個人的な意見に左右されず、検証可能な経験的データに基づいていた。因果関係も明確であり、「こうならば、これが起きる」といった構造を有していた。エンジニアやその他の専門家は、これらの標準規格を信頼し、品質向上、コスト削減、安全性向上に活用することができた。
その後、1970年代に入ると、品質マネジメントシステム規格が次第に注目を集めるようになった。もともとは、明快かつ鋭い文体で記された数ページのガイドライン(BS 5750:1979)にすぎなかったものが、現在では、内容を完全に理解するためにさらに補助文書を要するほどの膨大な文書群(ISO 9000:2015)へと膨れ上がった。残念ながら、我々の見解では、ISO 56000規格群もまた、国際標準化機構(ISO)が推進する、肥大化し検証困難な「付け焼き刃的な」標準規格の現代的な系譜を色濃く受け継いでいる。
2. 非倫理的な行為や利益相反の履歴
ISOは成長を遂げ、標準規格の世界を徐々に統合していった。そしてある時点で、標準規格の印刷および販売を主要な事業と位置づける決定を下した。そうした標準規格の導入によってエンドユーザーにもたらされる利益などは忘れ去られ、とにかく数を増やして発行し続ける姿勢が取られた。いわゆる「認証証明書の工場」(組織がISO認証を低価格で品質管理なしで購入できる場所)と戦うのでなく、むしろそのような大量生産モデルに邁進する道を選んだのである。
もう一つの問題は、ISOにおいて特定の規格群を策定する組織単位である各種技術委員会の実務担当者が、徐々に監査員やコンサルタントに置き換えられていったことである。これらの人物は、自ら規格の策定に関与しながら、規格が正式に施行される前にその認証取得のためのガイドを発行していたのである。クリストファー・パリスは、ISO 56001の少なくとも一人の作成者に利益相反の問題があることを含め、ISOの不正行為を綿密に記録している。標準規格が独立かつ客観的であるべきという理念は、もはや形骸化していると言わざるを得ない。
3. ISOマネジメントシステム認証の取得
かつて、企業組織はISO 9001品質マネジメントシステムやISO 14001環境マネジメントシステムといったISO規格に依存して事業運営されていた。しかし、今日では、認証工場など、上記に挙げた様々な問題により、認証取得は実際のシステムや企業のパフォーマンスと完全に切り離されてしまった。今や、それは大々的な歌舞伎の演目のような様相を呈しており、組織は書類上で体裁を整え、監査人はそれが実態であるかのように装い、認証印を押した別の書類がどこかに掲示されるだけとなっている。言い換えれば、品質マネジメントシステムの導入にISO 9001が必須でないのと同様に、イノベーション・マネジメントシステムの導入にISO 56001は必要ない。むしろ、ISO 56001がない方が成果を上げられる可能性すらある。
では、代替案は何か?
発行されているISO 56000規格をすべて揃えるには1200ユーロかかる。そのお金があれば、同じ金額でイノベーション・マネジメントに関する優れた書籍を40冊購入することが可能である。
実際に、イノベーション・マネジメントを深く探求し、実践的なノウハウを得ることに関心があるのであれば、以下の10冊の書籍を心から推薦したい。
- Tendayi Viki、Dan Toma、Esther Gons著『The Corporate Startup(邦訳:「イノベーションの攻略書」、翔泳社)』。イノベーション・エコシステムの構築と実装のための包括的なマニュアル。
- Richard Rumelt著『The Crux(邦訳:「戦略の要諦」、日経BP 日本経済新聞出版)』。健全な戦略とはどのようなものかを理解し、特定のテーマについて戦略策定して明確なツールとテクニックを提供するために役立つ。
- Rita McGrath著『Discovery Driven Growth(邦訳「ディスカバリー・ドリブン戦略」、東洋経済新聞社)』。企業のあらゆる事業機会を特定、管理、活用するための包括的なプロセスを提示。
- Greg Satell著『Mapping Innovation』。成功につながる可能性が最も高い最適なイノベーション戦略を特定するための使いやすいフレームワークと、独自のイノベーション・プレイブックを作成するためのステップバイステップガイドを提供。
- Constatinos Markides著『Game Changing Strategies』。ビジネスモデル・イノベーションと両利き経営について、あまり知られていない事例を多数紹介している優れた書籍
- Tony Ulwick著『What Customers Want』。ジョブ理論(JTBD:Jobs-To-Be-Done)と成果主導型イノベーションの入門書として最適。
- Cris Beswick、Derek Bishop、Jo Geraghty著『Building a Culture of Innovation』。ビジネスにイノベーション文化を設計し、定着させるための実践的なフレームワークを提示。
- Scott Anthony、Clark Gilbert、Mark Johnson著『Dual Transformation』。差し迫ったディスラプションに直面したビジネスを変革するための、実践的かつ持続可能なアプローチを提案。
- Douglas Hubbard著『How to Measure Anything』。あらゆるものに対して、意味のある指標を設計するための測定方法についてのガイド。
- Dan Toma、Esther Gons著『Innovation Accounting』。戦略からポートフォリオ、イノベーションチームに至るまで、イノベーションの測定と追跡に必要なすべての知識を網羅。
イノベーション主導の成長への道は、標準化されたチェックリストに従うことに依存するのではなく、自社の特性、戦略的ニーズ、そして何よりも価値創造プロセス(すなわちイノベーションプロセス)を理解することにかかっている。言い換えれば、成功は標準化されたシナリオに従うことではなく、真にインパクトがあり、組織の個々のニーズと志向に適合したイノベーション・システムを構築することによってもたらされるものである。ただし、それは一つの四半期で実現できるようなものではなく、規律と忍耐を要する取り組みである。
しかしながら、もし求めているのが、実質的な成果がほとんどないにもかかわらず、自社があたかもイノベーションに秀でているように見せかけることであったり、実質よりもイメージを重視する企業として、壁やPowerPoint資料に表示するための認証バッジを手に入れたいということであったり、あるいは取締役会に対して過去および将来のイノベーション予算を正当化するための材料が欲しいというだけであれば、イノベーション・マネジメントに関するISO規格は、まさにその目的に合致するものであるかもしれない。
本ブログは、ブルーノ・ペシェツ氏とダン・トマ氏の共著によるものです。
いかがでしたでしょうか。弊社では、ダン・トマ氏が欧州企業向けに導入支援を進めているイノベーション・システムを日本企業にも普及させるべく活動しております。ご興味の方は是非お問い合わせください
次回のブログは「失敗コストと失敗率("Cost of Failure vs. Rate of Failure")」という、イノベーションの取り組みにおいて上手に失敗するためのベストプラクティスについてのお話です。
WRITER

- 渡邊 哲(わたなべ さとる)
-
株式会社マキシマイズ シニアパートナー
Japan Society of Norithern California日本事務所代表
早稲田大学 非常勤講師
東京大学工学部卒。米国Yale大学院修了。海外の有力ITやイノベーション手法の日本導入を専門とする。特に海外ベンチャー企業と日本の大手企業や団体との連携による新規事業創出に強みを持つ。三菱商事、シリコンバレーでのベンチャー投資業務等を経て現職。ビジネスモデル・ナビゲーター手法の啓蒙活動をはじめ、日本のイノベーションを促進するための各種事業を展開中。
「アントレプレナーの教科書」「ビジネスモデル・ナビゲーター」「イノベーションの攻略書」「DXナビゲーター」「イノベーション・アカウンティング」を共訳/監訳。