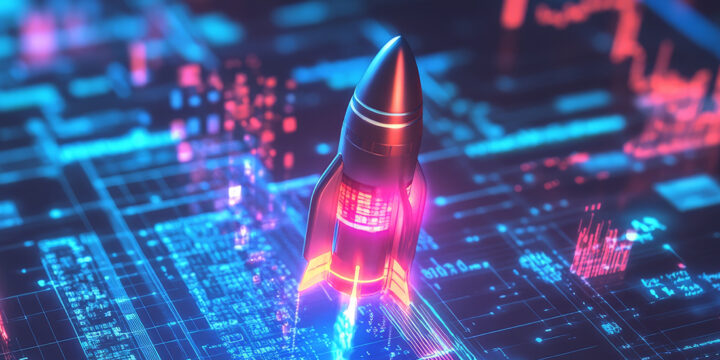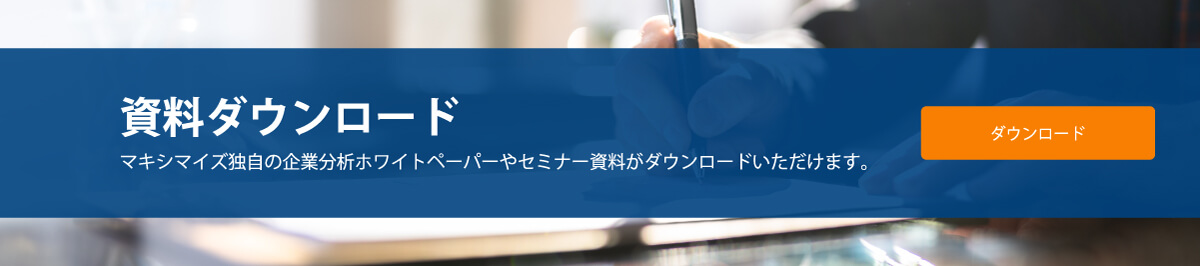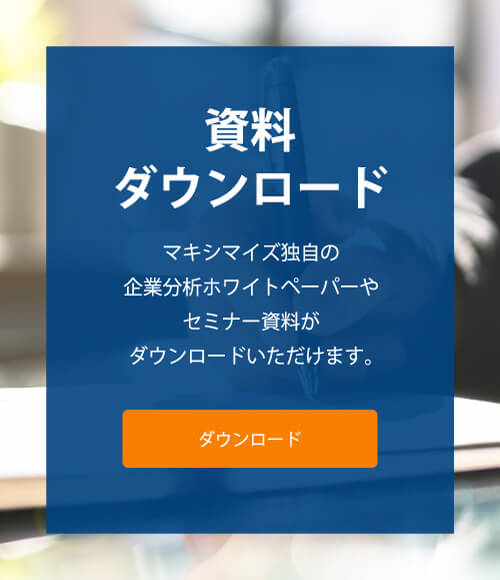失敗コストと失敗率("Cost of Failure vs. Rate of Failure")
みなさんこんにちは。マキシマイズの渡邊です。今回も書籍『イノベーションの攻略書(原題:The Corporate Startup)』、『イノベーション・アカウンティング(原題:The Innovation Accounting)』の著者であるダントマ氏のブログ記事をご紹介します。
今回は、「失敗コストと失敗率("Cost of Failure vs. Rate of Failure")」という、イノベーションの取り組みにおいて上手に失敗するためのベストプラクティスについてのお話です。では本文をお楽しみください。
失敗コストと失敗率("Cost of Failure vs. Rate of Failure")
2024年3月21日
ダン・トマ氏
失敗コストと失敗率(ダン・トマ氏が"OUTCOME社ウェブサイト"に掲載したブログ記事を、本人の許可を得て翻訳、掲載しています)

本ブログ記事の要点
- 「失敗率でなく失敗のコストに焦点を当てる」という意思決定をすることで、企業のイノベーションシステムに多くの好ましい結果をもたらす。
- 失敗のコストを追跡することで、費用対効果の高い検証実験やプロトタイピングを中心とした思考様式が促進される。一方、失敗率を重視すると、リーダーはイノベーション工程の初期段階から勝者を見極めようとして保守的になり、逆に一旦進め始めたプロジェクトについては不可能なことでも無理に進めるようとしがちになる。
- 失敗コストを追跡することで、迅速な意思決定が促される。失敗コストが高い場合には、イノベーションプロセスにおいて、事業アイデアに見切りをつけるまでに時間がかかりすぎ、その結果として無駄なコストが膨らんでいる可能性がある。
- 失敗コストを追跡することにより、自社の組織文化について多くのことが明らかになる。失敗コストが高い場合には、誠実な姿勢や率直な報告が十分に許容されない職場環境である可能性がある。
- 失敗のコストを追跡すると、予算内で1年間にどれだけの件数の取り組みを開始可能かを把握できる。
今日、多くの企業がイノベーションを自社の成長と事業継続性の礎と捉えていることは疑いようがない。企業がイノベーション主導の成長を目指す中で、イノベーションへの賢い投資を優先することが不可欠となっている。その結果、イノベーション投資の成功率が非常に重視されるようになった。成功率は、開始されたパイロットプロジェクトのうち事業の実行段階にまで至った件数、事業の成熟段階にまで達した事業アイデアの数、さらにアイデア段階から実際に製品化された件数などの指標によって測定される。これらはすべて、一般に「失敗率」と呼ばれる指標の関連指標である。
ところが、これらの指標は重要であるように見えても、実際には「失敗のコスト」という別の指標の方が、企業のイノベーションシステムに対してより広範な影響を及ぼす。「失敗のコスト」は、ほとんどの企業で議論されることも、測定されることも、最適化されることもない指標であるが、イノベーション主導の成長を真剣に志向する企業にとっては、極めて大きな変革をもたらす可能性を秘めている。
「失敗率」を追跡することでイノベーションの取り組みの成功に関する洞察が得られる一方で、この指標のみに焦点を当てると、継続的な改善の文化が育まれない可能性がある。「失敗のコスト」に視点を移すことで、イノベーションの全体像をより包括的に把握することが可能となる。
イノベーションにおいてコスト中心のアプローチを採用することは、「費用対効果の高い検証実験およびプロトタイピングに重点を置く思考様式」を促進する。このアプローチは、すべての事業アイデアが初期段階から成功するとは限らないという前提を受け入れ、財務的に責任ある方法で失敗から学ぶことの重要性を強調するものである。特に経営幹部においては、「成功の見えている事業アイデア」を選別しようとするのでなく、イノベーション戦略に合致したすべての事業アイデアに対して検証実験を許容する姿勢へと転換することで、「失敗率」ではなく「失敗のコスト」を追跡することによる、より大きな恩恵を享受することが可能となる。
さらに、「失敗のコスト」を追跡することで、「迅速な意思決定が可能になる」。失敗のコストが高い場合には、事業アイデアに見切りをつけるまでに過度な時間を要するイノベーションプロセスが社内に存在していることを示唆している可能性がある。このような状況では、より有望な事業へのリソースの再配分が遅れ、結果としてイノベーション・ファネル全体の効率性が損なわれている恐れがある。
さらに、失敗のコストは「企業文化」を如実に反映する指標でもある。「失敗のコスト」が高いことは、誠実さと透明性が欠如していることを示しており、何がうまく機能し何が機能しないのか、あるいは顧客が真に求めているものは何なのかといった率直なコミュニケーションが阻害されている可能性がある。このような洞察は、イノベーションを促進する企業文化を醸成しようとするリーダーにとって極めて重要である。
「失敗のコスト」を正しく理解することにより、企業は与えられた予算の範囲内で実行可能な取り組みの件数について、根拠に基づいた意思決定を行うことが可能となり、過剰なコミットメントを防ぎ、現実的なイノベーション・ポートフォリオを構築できる。「失敗率」が重要な指標であることに変わりはないが、それを「失敗コスト」と併せて考慮することにより、不要な財務的負担を避けながら、失敗から学ぶという姿勢の重要性がはっきりと強調される。
結論として、「失敗のコスト」を追跡することは、企業のイノベーションシステムを最適化する上で極めて重要である。「失敗率」から、失敗した事業の財務的影響に視点を移すことにより、企業は、責任ある検証実験、迅速な意思決定、ならびにリソースの最適化といった、持続的に継続可能なイノベーションと長期的な事業の成功に不可欠な企業文化を育むことができる。
イノベーションを、企業が1,000ドルの予算で宝くじに投資することに例えて考えてみるとよい。当選確率が同じである場合、1枚10ドルの宝くじを100枚購入するのと、1枚100ドルの宝くじを10枚購入するのとでは、どちらを選ぶのが適切だろうか。この比喩は、限られた予算内でコストを適切に管理し、成功の可能性を最大化することの重要性を示唆している。
本ブログ記事は、もともとイノベーション・アカウンティングのブログに掲載されたブログ記事の文面を一部変更したものです。
いかがでしたでしょうか。弊社では、ダン・トマ氏が欧州企業向けに導入支援を進めているイノベーション・システムを日本企業にも普及させるべく活動しております。ご興味の方は是非お問い合わせください
次回のブログは「イノベーション会計はすべての企業に役立つ("Innovation Accounting is for Everyone")」という、企業各社のイノベーション促進の仕組みの成熟度に応じたイノベーション会計の活用法についてのお話です。
WRITER

- 渡邊 哲(わたなべ さとる)
-
株式会社マキシマイズ シニアパートナー
Japan Society of Norithern California日本事務所代表
早稲田大学 非常勤講師
東京大学工学部卒。米国Yale大学院修了。海外の有力ITやイノベーション手法の日本導入を専門とする。特に海外ベンチャー企業と日本の大手企業や団体との連携による新規事業創出に強みを持つ。三菱商事、シリコンバレーでのベンチャー投資業務等を経て現職。ビジネスモデル・ナビゲーター手法の啓蒙活動をはじめ、日本のイノベーションを促進するための各種事業を展開中。
「アントレプレナーの教科書」「ビジネスモデル・ナビゲーター」「イノベーションの攻略書」「DXナビゲーター」「イノベーション・アカウンティング」を共訳/監訳。