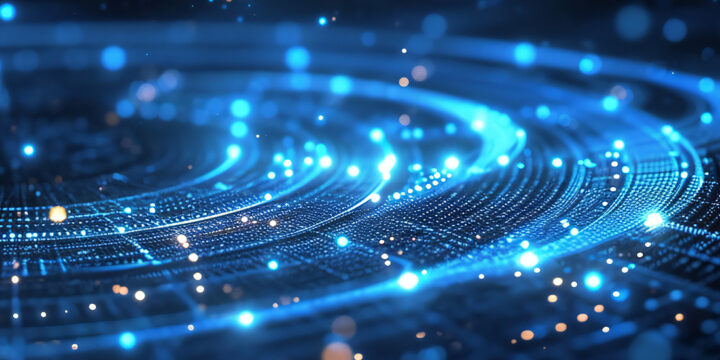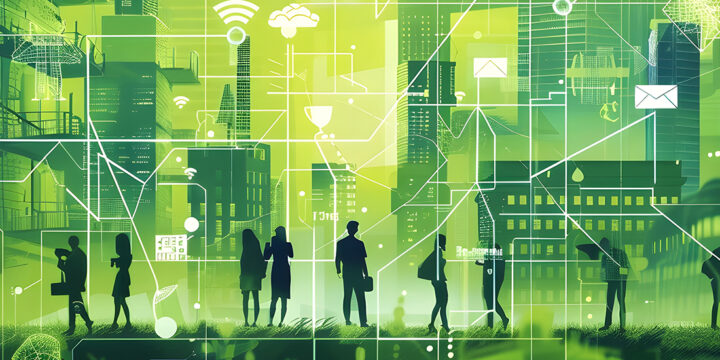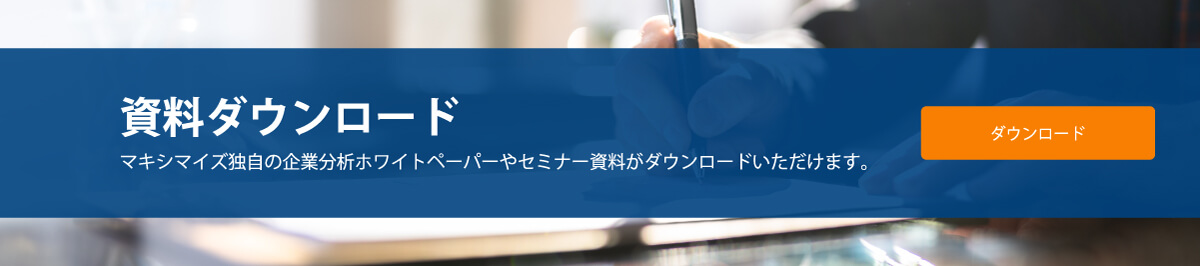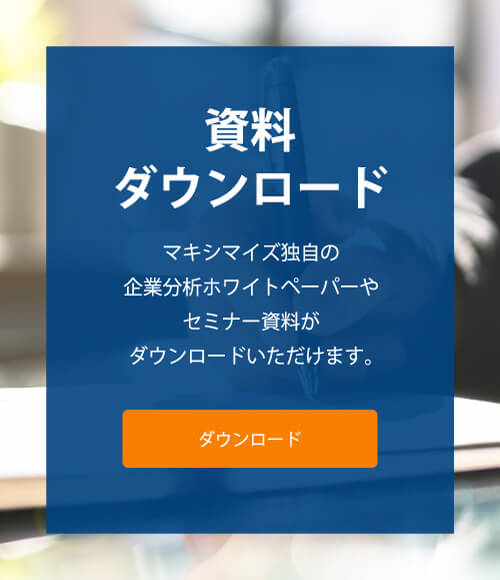目標を持つことは戦略を持つことを意味しない("Having Goals Doesn’t Mean You Have a Strategy")
みなさんこんにちは。マキシマイズの渡邊です。今回も書籍『イノベーションの攻略書(原題:The Corporate Startup)』、『イノベーション・アカウンティング(原題:The Innovation Accounting)』の著者であるダントマ氏のブログ記事をご紹介します。
今回は、「目標を持つことは戦略を持つことを意味しない("Having Goals Doesn’t Mean You Have a Strategy")」という、企業における戦略と目標の違い、及びその両方を適切に設定することの重要性についてのお話です。では本文をお楽しみください。
目標を持つことは戦略を持つことを意味しない("Having Goals Doesn’t Mean You Have a Strategy")
2024年9月10日
ダン・トマ氏
目標を持つことは戦略を持つことを意味しない(ダン・トマ氏が"OUTCOME社ウェブサイト"に掲載したブログ記事を、本人の許可を得て翻訳、掲載しています)

残念ながら、多くの取締役会における議論では、「目標」と「戦略」という用語がしばしば同義のものとして扱われている。これは、おそらく両者が互いに不可分であり、一方がなければ他方も成立し得ないという事実に起因していると考えられる。しかしながら、これらは本質的に異なる概念である。目標とは、企業が達成を目指す望ましい成果や到達点を指し、戦略とは、その目標を達成するために企業が採用すべき、あるいは採用を検討している計画や方針を意味する。この違いを正しく理解することは、持続的成長を実現するうえで極めて重要である。
言い換えれば、目標とは「何(What)」を達成したいかを定義するものであり、戦略とはそれを「どのように(How)」達成するかを定義するものである。この違いは単に言葉の意味の問題ではなく、効果的な経営およびリーダーシップの根幹を成すものである。戦略を伴わずに目標のみを設定することは、企業における価値創造プロセスに対する理解の欠如、さらには企業のミクロおよびマクロ環境に対する認識の不十分さを示すものである。
要点
- 目標は「何(What)」を定義し、戦略は「どのように(How)」を定義する。
- 戦略を持たずに目標のみで企業経営を行うと、非効率や長期的な失敗を招く可能性が高い。
- 単なる目標管理から戦略的な経営へと移行するには、リーダーはビジネス目標の「どのように(How)」と「なぜ(Why)」を掘り下げるべく自問自答する必要がある。
会社の目標を戦略そのもの(あるいは行動を起こすのに十分なもの)と考えることのリスクは、テクノロジーへの適応、競争優位性、従業員のエンゲージメントなど、様々な側面に影響を及ぼす。目標設定を戦略策定と誤認した組織は、長期的成長に深刻な影響を及ぼしかねない多種多様な課題に直面することが多い。
たとえば、目標のみに基づいてリソース配分の意思決定を行うと、「短期主義」に陥る可能性がある。短期主義とは、目先の利益や目標で示された四半期ごとの数値達成に重点が置かれ、長期的な成功や、それらの目標をどのように達成するかというプロセスの長期的影響が軽視される傾向を指す。
さらに、戦略的意図を問うことなく、目標のみに基づいてマネジメントを行うと、「取り組みが散漫になり、実行される行動の一貫性が著しく欠如する」結果を招くことが多い。将来的な影響や持続可能性を考慮せず、差し迫った課題への対処に終始するような行動が取られるためである。こうした状況は、機会の損失、リソースの非効率な活用、ひいては長期的かつ持続的な成長の実現を阻む要因となりうる。
また、「目標設定だけでは「なぜ」が伝わらない」。その結果、従業員は自らが戦略的な議論に関与しているという実感を得られず、単にスプレッドシート上の数値を達成するための手段として扱われているように感じ、モチベーションの低下を招くおそれがある。人は行動の背後にある「なぜ」を知りたいのだ。なぜなら、それが理解、関与、そして信頼を育むからである。ハーバード・ビジネス・レビューの調査(Amabile & Kramer, 2011)によれば、自らの業務の目的を理解している従業員は、より高いモチベーションを持ち、優れたパフォーマンスを発揮する傾向にある。意思決定の根拠を共有することは、従業員の知性と自律性を尊重する姿勢を示すものであり、信頼と透明性の構築に寄与する。また、従業員に対して必要な背景情報を提供することで、主体的な意思決定と行動を促進し、エンパワーメントを実現することにもつながる。
企業において、戦略を伴わない目標設定は、多くの場合、非効率性や長期的な失敗につながる。例えば、ノキアがその典型例である。かつて携帯電話市場で圧倒的なシェアを誇っていたノキアは、明確な目標を掲げていたが、スマートフォンへの移行に戦略的に適応することができなかった。アップルやアンドロイドといった競合他社が急速に革新を遂げる中、ノキアは既存製品に注力し続けた。このような戦略的な見通しの欠如が、ノキアを市場のリーダーから業界の傍流へと転落させる要因となったのだ。
同様に、ブラックベリーの事例もまた重要な教訓である。セキュアなメッセージングサービスと物理キーボードで知られていたブラックベリーは、タッチスクリーン革命とアプリ・エコシステムの重要性を認識し、適応することができなかった。対応の遅れと戦略の一貫性の欠如が、結果的に市場シェアの大幅な喪失につながったのだ。
目標は方向性を示すものであるが、明確かつ実行可能な計画が伴わなければ、その達成に向けた進捗は場当たり的かつ受動的なものとなりやすい。単なる目標管理から戦略的マネジメントへと移行するためには、リーダーは自社のビジネス目標における「どのように(How)」と「なぜ(Why)」を深く掘り下げる本質的な問いを自らに投げかける必要がある。以下に示すのは、我々が戦略策定プロセスにおいて用いている質問の一部であり、クライアントが目標ベースの意思決定から戦略的意思決定へと移行する際に実際に効果を上げてきたものである。
1. テクノロジー、競争、消費者行動における重要な課題は何か。
これらの課題を正確に把握することは、ビジネスに影響を与える外部要因を特定するのに役立つ。そうした要因を認識することで、それらを乗り越えるためのより効果的な戦略立案が可能となる。
2. これらの目標やターゲットを達成することは、自社にとってどのような点で重要なのか?
目標の重要性を明確にすることで、全員がその目的を理解し、それに基づいて努力の方向性をそろえることができる。
3. 今後の3~5年間において、自社にとってテクノロジー、競争、消費者行動に関する最も重要な課題は何であるか。それらのうち、自社にとってどれが問題であり、どれが機会といえるか。
将来を見据えることで、予測される問題と機会を的確に捉えることが可能となり、受動的でなく能動的な計画策定を実施できる。
4. 過去3~5年間に自社が実施した取り組みの中で、成功したと言えるものは何か?
過去の成功を振り返ることで、再現すべき価値のある効果的な戦略や活動が浮かび上がってくる。
5. 過去3~5年間に貴社が実施した取り組みの中で、成功しなかったと言えるものは何か?成功を妨げた要因は何であり、どのような改善の余地があったのか。
過去の失敗を分析することで貴重な教訓が得られ、同様の過ちを繰り返すことを防ぐことができる。
6. 現在、自社で解決に取り組んでいる優先課題は何か?これらの優先課題に対処するために、どのような取り組みを既に実施しているか、または現在すでに投資しているか?
現在の優先事項を明確にすることで、最も差し迫った課題にリソースと労力を集中できる。
7. 自社の組織構造や基本方針に起因する、注目すべき課題や困難は何か?これらは、前の質問で特定した事項の進捗を妨げるほど重大なものか?具体的にはどんな課題か?
企業内の組織構造および基本方針の問題に対処することで、戦略的成功に対する内部的な障壁を取り除くことができる。
効果的なリーダーシップとは、野心的な目標を設定し、それを追跡するだけでは成り立たない。自社の内外の環境を考慮した、綿密に練られた戦略が必要である。適切な問いを立て、過去の成功と失敗から学ぶことにより、企業は短期的な目標の達成にとどまらず、長期的な成長への道を切り拓く、強固な戦略を策定できるのだ。
結論として、目標を持つことは不可欠だが、それは成長の要素の一つに過ぎない。持続可能な成功を達成するには、企業は目標と、現在の課題と将来の機会の両方に対応する明確で実行可能な戦略を併せ持つ必要がある。このバランスの取れたアプローチにより、企業の努力は目先の成果の追求にとどまらず、長期的なビジョンおよび企業の健全な成長と整合するものとなる。
本ブログ記事は、もともとCorporate Startupのブログに掲載されたものです。
いかがでしたでしょうか。弊社では、ダン・トマ氏が欧州企業向けに導入支援を進めているイノベーション・システムを日本企業にも普及させるべく活動しております。ご興味の方は是非お問い合わせください
次回のブログは「企業でESGを実現するために必要なこと("What It Takes to Make ESG Happen in Your Company")」という、ESGを単に道徳的責務というだけでなく、ビジネス上のメリットを生み出すイノベーションの取り組みとすることについてのお話です。
WRITER

- 渡邊 哲(わたなべ さとる)
-
株式会社マキシマイズ シニアパートナー
Japan Society of Norithern California日本事務所代表
早稲田大学 非常勤講師
東京大学工学部卒。米国Yale大学院修了。海外の有力ITやイノベーション手法の日本導入を専門とする。特に海外ベンチャー企業と日本の大手企業や団体との連携による新規事業創出に強みを持つ。三菱商事、シリコンバレーでのベンチャー投資業務等を経て現職。ビジネスモデル・ナビゲーター手法の啓蒙活動をはじめ、日本のイノベーションを促進するための各種事業を展開中。
「アントレプレナーの教科書」「ビジネスモデル・ナビゲーター」「イノベーションの攻略書」「DXナビゲーター」「イノベーション・アカウンティング」を共訳/監訳。