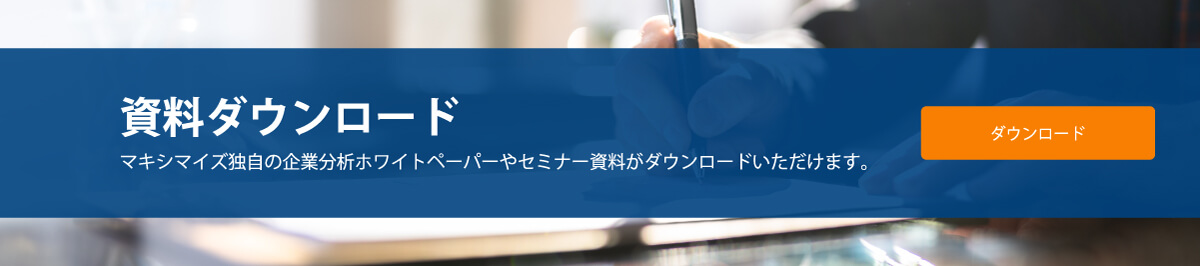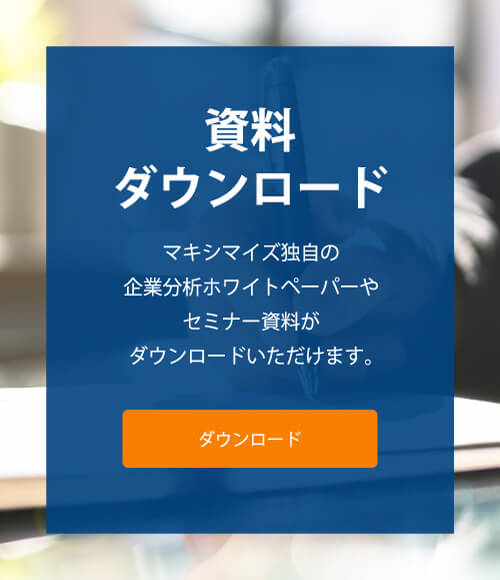「変革を起こしたいなら、「ノー」と言うことを学ぼう("If You Want To Innovate, Learn To Say “No”If You Want To Innovate, Learn To Say “No”")
みなさんこんにちは。マキシマイズの渡邊です。今回も書籍『イノベーションの攻略書(原題:The Corporate Startup)』、『イノベーション・アカウンティング(原題:The Innovation Accounting)』の著者であるダントマ氏のブログ記事をご紹介します。
今回は、「変革を起こしたいなら、「ノー」と言うことを学ぼう("If You Want To Innovate, Learn To Say “No”If You Want To Innovate, Learn To Say “No”")」という、イノベーションの対象を絞り込むことの重要性についてのお話です。では本文をお楽しみください。
「変革を起こしたいなら、「ノー」と言うことを学ぼう("If You Want To Innovate, Learn To Say “No”If You Want To Innovate, Learn To Say “No”")
2023年9月13日
ダイアナ・ジョセフ氏
変革を起こしたいなら、「ノー」と言うことを学ぼう(書籍の著者であるダイアナ・ジョセフ氏、ダン・トマ氏、エスター・ゴンス氏が"OPEN INNOVATION WORKSウェブサイト"に掲載したブログ記事を、著者らの許可を得て翻訳、掲載しています)

専門家たちは、世界はますます不安定で、不確実で、複雑かつ曖昧になっていると指摘している。これはまさに「VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)」の福音といえる。「変革か死か」という掛け声のもと、大規模な変革プロジェクトが次々と始動している。世界中の経営幹部たちは、組織の再編と再構築に奔走しているが、結局のところ、組織の再編と再構築をむやみに繰り返すだけに終わっている。(太字フォント)
状況はさらに悪化している。PwCの2014年のレポートでは、企業の回答者の65%が変化疲れを訴え、従業員の44%が自分にどんな変化を求められているのかわからないと不満を述べ、38%が変化することに同意していないと回答している。ガートナーが2020年に実施したより最近の調査では、コロナ禍の期間に変化疲れの傾向が倍増したことが明らかになっている。
このような狂騒は終わらせる必要がある。行動力のあるリーダーとして見られたい経営幹部は、あまりにも多くの取り組みを立ち上げているが、そのほとんどがプラスの効果につながっておらず、むしろ幹部以外の従業員はメンタルヘルスの悪化に苦しんでいる。解決策は、取り組みを増やすのではなく、減らすことだ。取り組みの数を絞り込み、成功を確実にするために、それぞれの取り組みにより強くコミットメントするべきである。
何故変革が失敗するのか?
これは我々が何度も見てきたお決まりのパターンだ。野心的な新リーダーが就任し、変革の取り組みを開始する。キックオフミーティングが開催され、複数年にわたる計画に向けて社員を鼓舞すべく、大規模な社内広報キャンペーンが展開される。コンサルタントが起用され、社員には「この計画に必ず協力するように」と、明確な伝達がなされる。
2年後、当事者であるリーダーは自身の変革型リーダーシップという神話を次の企業に売り込み、転職して会社を去る。元の企業には、同様に野心的な別の幹部が現れ、独自の変革アイデアを持ち込む。従来の取り組みは打ち切られ、再びキックオフミーティングが開催され、社内広報キャンペーンが展開され、コンサルタントが起用され、従業員は協力を求められる。そして、このサイクルが延々と繰り返されるのである。
責任を問うべき点は山ほどある。しかし、率直に言って、真の成果よりもキックオフを称賛する傾向があることが最大の問題だ。これには文化的な要因もあれば、現代のトレンドを反映しているという側面もある。四半期ごとの業績指標に過度に固執すると、短期的な成果ばかりに重点が置かれすぎてしまう。これに、経営陣の在任期間の短期化という企業全般の傾向が加わることで、変革プロジェクトが完了する前にリーダーが退任するという事態が増加しているのだ。
これらすべてには代償を伴う。経済統計のデータを見れば、生産性の伸びが過去の世代と比べて著しく低下していることが一目瞭然だ。特に米国においては、ホワイトハウスの調査で、過去数十年間にわたり様々な指標において競争力が著しく低下していることが明らかになっている。
「ノー」と言うことの力
スティーブ・ジョブズのアップル在任期間を振り返るとき、多くの人がまず思い浮かべるのは、彼のリーダーシップのもとで発売された数々の製品である。しかし、彼がアップルで成し遂げた最も重要な功績は、製品の創出でなく、むしろ製品の廃止であった。1997年にアップルへ復帰した際、ジョブズは、長年にわたる無秩序な経営の結果、製品ラインアップが過剰に膨れ上がっている現状を目の当たりにした。彼が最初に着手したのは新たなイノベーションの導入ではなく、製品ラインアップの徹底的な見直しであり、その結果、全製品の70%を廃止したのである。
「ジョブズの偉大な強みの一つは、集中する方法を知っていたことだ」と、伝記作家のウォルター・アイザックソンはのちに記している。「何をしないかを決めることは、何をするかを決めるのと同じくらい重要だ」と、伝説のCEOであるジョブズの言葉を引用して彼は述べている。「これは企業にも、製品にも当てはまる。」
ある時点で、いらだちを募らせたジョブズは「やめろ!」と周囲を一喝した。マジックペンを手に取ると、ホワイトボードに向かって、「コンシューマー」と「プロ」を縦軸、「デスクトップ」と「ポータブル」を横軸とする典型的な2×2のマトリックスを描いた。そして彼は、アップルはこの4象限それぞれに対応する4つの優れた製品のみを開発する、と宣言したのだ。
ジョブズは在任中この規律を貫き続け、その後10年間で、iMac、iPod、iPhone、そしてiPadを次々と発表した。ほんの数個の製品だけで、アップルは世界で最も価値のある企業へと成長したのである。イノベーション主導の企業になるということは、数多くのアイデアを打ち出すことではなく、本当に重要なアイデアに集中し、それをどのように実現するかを見出すことなのだ。
決断の時
変革について話し合う機会がますます増えている一方で、実際に実現されることは逆に減っているように思われる。これは偶然ではない。変化や変革とは、単にアイデアを出し、華々しいキックオフイベントを行い、その後に大規模なコミュニケーションキャンペーンを展開することではない。それらのアイデアを、人々が真に関心を寄せる課題に対する、インパクトある解決策へと転換することこそが、変革の本質なのだ。
議論ばかりが先行し、実質的なインパクトが著しく不足しているのが現状である。変化とは本来、疲弊した職場にさらなる重荷を課すものでなく、インスピレーションの源であるべきだ。今こそ、真に意味のある変化に集中すべき時だ。大半の企業にとって、それは取り組みの数を絞り込み、一つひとつを確実に完遂する覚悟を決めることを意味する。
これを効果的に行うためには、リーダーが「ノー」と言える力を身につける必要がある。あらゆる組織にとって、限られた資源を最大限に活用することは不可欠であり、そこでは選択を迫られる。ひとつのことを追求するためには、他を諦めるという決断が必須なのだ。むやみにあれこれ手を出しても成果は得られない。進むべき方向を定め、確実に前進することが求められる。
それは言うほど簡単ではない。特定の目標にコミットするということは、選択肢を狭めることを意味する。困難な状況でもプロジェクトをやり遂げるには、勇気と粘り強さが必要である。だからこそ、それを一貫して実行できるリーダーはごくわずかである。しかし、証拠は明白である。競争に勝ちたいのであれば、それが必須なのだ。
いかがでしたでしょうか。弊社では、ダン・トマ氏が欧州企業向けに導入支援を進めているイノベーション・システムを日本企業にも普及させるべく活動しております。ご興味の方は是非お問い合わせください
次回のブログは「企業スピンアウトの技法:いつスピンアウトするのか?どのようにスピンアウトするのか?("The Art of Corporate Spin-Outs: When to spin-out? How to spin-out?")」という、新規事業を親会社からスピンアウトする際に念頭に置くべき事項についてのお話です。
WRITER

- 渡邊 哲(わたなべ さとる)
-
株式会社マキシマイズ シニアパートナー
Japan Society of Norithern California日本事務所代表
早稲田大学 非常勤講師
東京大学工学部卒。米国Yale大学院修了。海外の有力ITやイノベーション手法の日本導入を専門とする。特に海外ベンチャー企業と日本の大手企業や団体との連携による新規事業創出に強みを持つ。三菱商事、シリコンバレーでのベンチャー投資業務等を経て現職。ビジネスモデル・ナビゲーター手法の啓蒙活動をはじめ、日本のイノベーションを促進するための各種事業を展開中。
「アントレプレナーの教科書」「ビジネスモデル・ナビゲーター」「イノベーションの攻略書」「DXナビゲーター」「イノベーション・アカウンティング」を共訳/監訳。