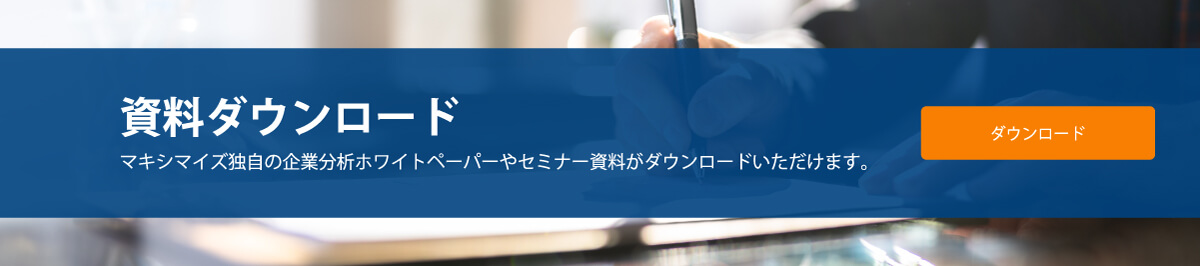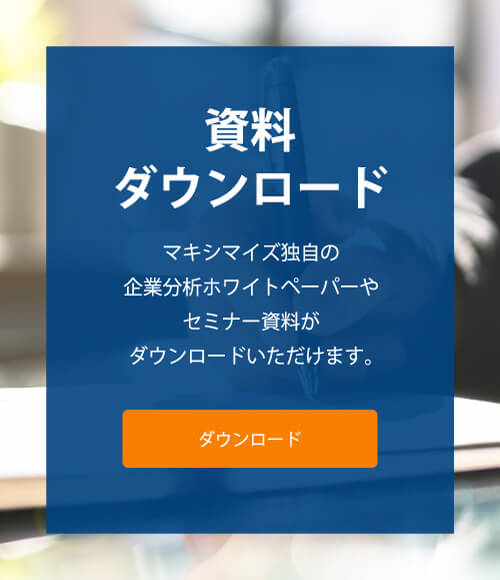企業スピンアウトの技法:いつスピンアウトするのか?どのようにスピンアウトするのか?("The Art of Corporate Spin-Outs: When to spin-out? How to spin-out?")
みなさんこんにちは。マキシマイズの渡邊です。今回も書籍『イノベーションの攻略書(原題:The Corporate Startup)』、『イノベーション・アカウンティング(原題:The Innovation Accounting)』の著者であるダントマ氏のブログ記事をご紹介します。
今回は、「企業スピンアウトの技法:いつスピンアウトするのか?どのようにスピンアウトするのか?("The Art of Corporate Spin-Outs: When to spin-out? How to spin-out?")」という、新規事業を親会社からスピンアウトする際に念頭に置くべき事項についてのお話です。では本文をお楽しみください。
「企業スピンアウトの技法:いつスピンアウトするのか?どのようにスピンアウトするのか?("The Art of Corporate Spin-Outs: When to spin-out? How to spin-out?")
2023年11月14日
ダン・トマ氏
企業スピンアウトの技法:いつスピンアウトするのか?どのようにスピンアウトするのか?(ダン・トマ氏が"OUTCOME社ウェブサイト"に掲載したブログ記事を、本人の許可を得て翻訳、掲載しています)

今日の不安定な経済環境において、イノベーションは、正しく実行されればもはや単なる流行語ではなく、企業の生命線といえる。企業は常に、革新的なアイデアに命を吹き込む独創的な手法を模索しており、その意味ではスピンアウトはイノベーションを現実的かつ実行可能にするための手段の一つに過ぎない。
「スピンアウト」とは、一般的に大学、研究機関、または大企業といった既存組織から新会社が設立されるプロセスを指す。この新会社、つまりスピンアウトは通常、親にあたる組織内で開発された研究やイノベーションから生まれる。スピンアウトの目的は、これらのイノベーションを事業化し、市場において実現可能な製品やサービスへと転換することである。スピンアウトは、先端テクノロジー、バイオテクノロジー、医薬品など、イノベーションと研究が重要な役割を担う産業において広く見られる。
したがって、スピンアウトは企業のイノベーションマネジメントと起業家精神が真正面からぶつかり合う場であると言っても過言ではない。しかし、スピンアウトを成功させるのは言葉で言うほど簡単ではない。2000年から2020年の間に10億ドル以上の価値を持つ350社以上の上場スピンアウト企業を調査したハーバード・ビジネス・レビューの調査によれば、分社化を進めた企業の50%は分社後2年経過しても新たな株主価値を創出できず、25%は分社化の過程で株主価値を大幅に棄損していることがわかった。
スピンアウトが理にかなっている理由
成功率の低さにもかかわらず、以下の理由から、スピンアウトは企業や大学にとって依然として非常に魅力的な選択肢である。
- 集中:大規模な組織においては、興味分野が多岐にわたることが一般的である。特定のイノベーションをスピンアウトすることで、分社化された新会社は当該イノベーションの開発と事業化に専念できるようになる。
- 起業家精神:スピンアウトは、研究者やイノベーターに起業家としての道を開くものであり、自身のアイデアを市場に投入し、その成果から経済的な利益を得る機会を提供する。
- 資金調達:スピンアウト企業は、ベンチャーキャピタルをはじめとする外部からの投資の対象となり得る。大規模組織内の一部門にとっては、外部からの資金調達を実現することは通常は難しい。
- 俊敏性: 新しく設立された小規模な企業は、市場の需要や変化に迅速に対応できることが多く、製品開発やマーケティング戦略において高い俊敏性を発揮できる。
- リスク管理:イノベーションが市場で失敗した場合でも、親会社の評判に直接影響することはない。リスクはスピンアウト企業に限定される。
- イノベーション エコシステム: スピンアウト企業は、地域や業界のイノベーション エコシステム全体に貢献し、競争を促進するとともに、さらなる技術革新の推進力となる。
スピンアウトを準備する際に注意すべき落とし穴
しかし、スピンアウトがどれほど魅力的であっても、移行を検討する前から親にあたる企業や組織が認識しておくべき落とし穴がいくつかある。
- 企業の中には、「主力事業の中核にあまりにも近い」新事業プロジェクトをスピンアウトするという意思決定を下す企業もある。Staples.com の事例がまさにその典型例である。同社の「販売チャネル」に関するシンプルなビジネスモデル革新の試みは、株主の反対を招いて中止を余儀なくされ、結果的にスピンアウトの大々的な失敗例へと転げ落ちた。
- 時には「目先の利益を優先するために長期的な戦略思考がないがしろにされる」こともある。本来であればスピンアウトを一つの独立した事業として捉えるべきところを、親会社がこれを負債や債務の帳消し手段として利用したり、コア事業の資金調達のための担保として扱ったりする場合があるのだ。
- 一部の企業は、「市場で自立して生き残るために必要なすべての要素が整っていない事業体をスピンアウトしてしまう」という過ちを犯すことがある。たとえば知的財産(IP)の観点から見ると、スピンアウトにおける重要な側面の一つは、親会社から新会社への知的財産の移転である。特許、著作権、その他の知的財産資産の使用に関する明確な合意は、将来的な法的リスクを回避するうえで不可欠である。仮に知的財産が親会社にとどまり、スピンアウト先の企業がそれに対して一切の変更を加えることができない場合、新設企業が市場の変化や顧客ニーズに柔軟に対応することは著しく困難となる。
スピンアウト実施の判断基準
スピンアウトの実現プロセスは、スピンアウト候補の選定、資金とリソースの確保、熟練した専門家チームの設立、そして最後に重要な点として、法的な枠組みの構築など、複数ステップで構成される。しかし、企業のリーダーにとってより重要なのは、新事業プロジェクトのポートフォリオの中からスピンアウトに適したプロジェクトと、社内に残すべきプロジェクトを見極めることである。
プロジェクトをスピンアウトさせるべきかどうかの決定は極めて重要であり、多くの場合、一旦進めたら元に戻せない意思決定である。経営者が十分な情報に基づいて適切な判断を下すためには、以下のような評価基準と検討事項が有効となる。
- 市場ポテンシャル:新しい事業アイデアの市場ポテンシャルを評価することが重要である。新事業で提供する製品やサービスに対する明確な需要が存在するか。スピンアウト候補となる事業の市場規模は、独立企業として存続できるだけの規模があるか。それとも、依然として親にあたる組織の中核事業からの資金的支援を必要とするのかを見極める必要がある。
- 戦略的整合性:将来のスピンアウト候補が、企業全体の戦略や目標と整合しているかを検討する必要がある。スピンアウトして外部に切り離すよりも、社内にとどめた方が企業の長期的目標にとっての貢献度が高くなるか。既存の製品・サービスのポートフォリオと調和しているか。社内にとどめた場合、既存の顧客層に混乱を招くおそれはないか、といった点を慎重に見極めるべきである。
- リソース配分:新規事業アイデアの開発およびスケールアップに必要なリソースを評価する必要がある。これには、資金、熟練した人材、インフラ、時間といった要素が含まれる。企業がこれらのリソースを社内で確保できるか、あるいはスピンアウトによって社外で実現する方が現実的かを判断すべきである。
- ビジネスモデル:スピンアウト候補のビジネスモデルが、親会社から独立した環境においても存続可能であるか、それとも「へその緒」が切れた瞬間に消滅してしまう脆弱なものであるかを評価する必要がある。逆に、そのビジネスモデルが既存の中核事業に対してあまりにも急進的であり、社内に留めた場合に企業内における「抗体反応」によって新事業が阻害されるおそれがないかについても十分に見極める必要がある。
- 競争優位性:競争環境を分析する。新たな事業アイデアには、それ自体に独自のセールスポイントや競争優位性があるか、それとも新事業の成功が親会社の中核事業に過度に依存しているかを見極める必要がある。
- 知的財産:事業アイデアに関連する知的財産を考慮する。製品/サービスを保護するために必要な特許、著作権、商標をスピンアウト企業側で保有できるかどうかを評価する。知的財産の明確な所有権は、スピンアウトの成功に不可欠である。
- チームの起業家マインド:スピンアウト企業が母艦である親会社から独立した後、その運営を担うチームを評価する必要がある。スタートアップを運営するための起業家精神、スキル、そして経験を備えているか?有能で意欲的なチームは、スピンアウト企業の成功に不可欠である。
- リスクと課題:新たな体制に伴って発生しうる潜在的なリスクと課題を特定する必要がある。これには、技術的な課題、規制および法的ハードル、市場受容リスク、競争などが含まれる。企業のリスク許容度と対応能力を評価することが求められる。
- 財務的実現可能性:徹底的な財務分析を行う。開発費用、市場参入コスト、継続的な運営費用などの推定コストを算出する。これを、対象プロジェクトがスピンアウトした場合と親会社に留まった場合の収益予測および潜在的な収益性の観点で比較検討する必要がある。
- 出口戦略:スピンアウトの長期的な出口戦略を検討する。自社は将来、スピンアウトした新会社の所有権を保持し続けるか、部分的に売却するか、それとも完全に売却するかを検討する必要がある。それぞれのシナリオが自社の目標および経営戦略に与える影響を評価すべきである。
- 法務およびコンプライアンス問題:スピンアウトがすべての法規制要件を遵守していることを確認する。これには、事業登録、各種ライセンス、許認可、および業界固有の規制が含まれる。
これらの基準に基づいて潜在的なスピンアウト候補を慎重に評価することにより、大企業は、ある事業アイデアをスピンアウトとして追求すべきか、それとも親会社内にとどめて他の手段を模索すべきかについて、十分な情報に基づいた意思決定を下すことができる。
競争の激しいビジネスの世界において、スピンアウトはイノベーション主導の成長を牽引する可能性を秘めた戦略的手段である。しかし、スピンアウトは繊細なバランスと綿密なデューデリジェンスを必要とする複雑な取り組みであり、企業のイノベーションパイプラインにあるすべての新規事業アイデアに適しているとは限らない。
いかがでしたでしょうか。弊社では、ダン・トマ氏が欧州企業向けに導入支援を進めているイノベーション・システムを日本企業にも普及させるべく活動しております。ご興味の方は是非お問い合わせください
次回のブログは「ISO規格がイノベーション管理において不十分な理由("Why ISO Standards Fall Short in Innovation Management")」という、イノベーションマネジメントにおけるISO規格の有用性についてのお話です。
WRITER

- 渡邊 哲(わたなべ さとる)
-
株式会社マキシマイズ シニアパートナー
Japan Society of Norithern California日本事務所代表
早稲田大学 非常勤講師
東京大学工学部卒。米国Yale大学院修了。海外の有力ITやイノベーション手法の日本導入を専門とする。特に海外ベンチャー企業と日本の大手企業や団体との連携による新規事業創出に強みを持つ。三菱商事、シリコンバレーでのベンチャー投資業務等を経て現職。ビジネスモデル・ナビゲーター手法の啓蒙活動をはじめ、日本のイノベーションを促進するための各種事業を展開中。
「アントレプレナーの教科書」「ビジネスモデル・ナビゲーター」「イノベーションの攻略書」「DXナビゲーター」「イノベーション・アカウンティング」を共訳/監訳。