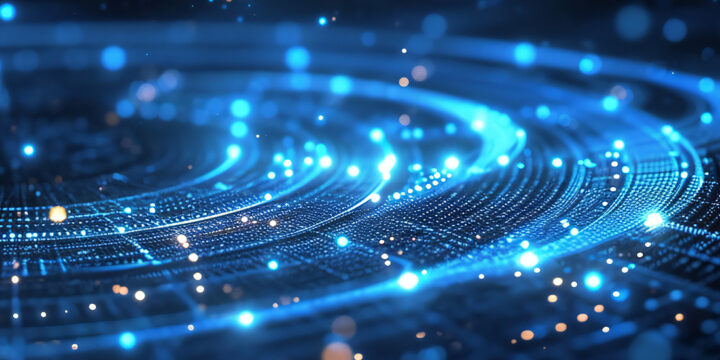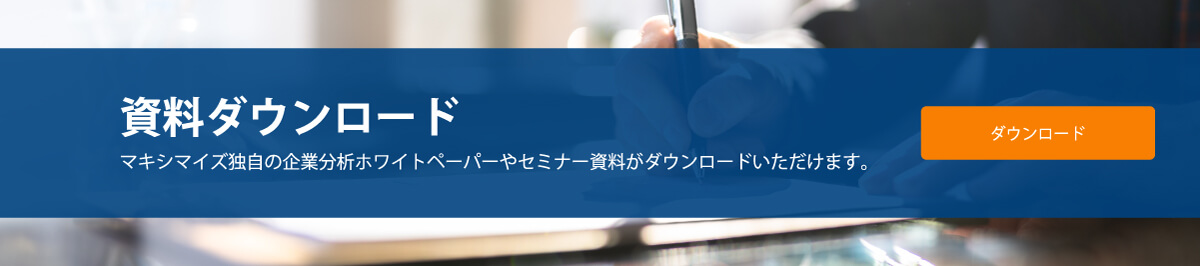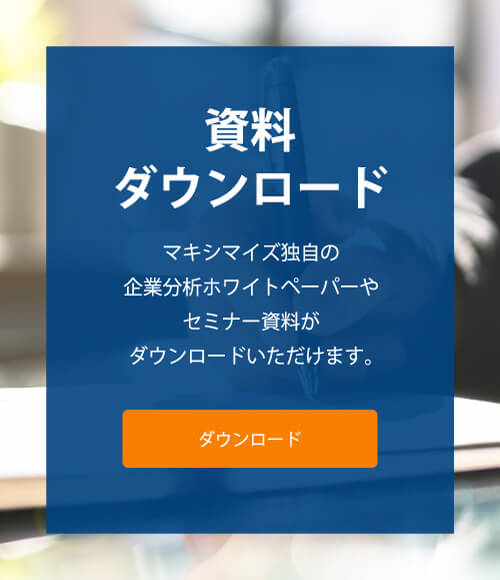イノベーション会計はすべての企業に役立つ("Innovation Accounting is for Everyone")
みなさんこんにちは。マキシマイズの渡邊です。今回も書籍『イノベーションの攻略書(原題:The Corporate Startup)』、『イノベーション・アカウンティング(原題:The Innovation Accounting)』の著者であるダントマ氏のブログ記事をご紹介します。
今回は、「イノベーション会計はすべての企業に役立つ("Innovation Accounting is for Everyone")」という、企業各社のイノベーション促進の仕組みの成熟度に応じたイノベーション会計の活用法についてのお話です。では本文をお楽しみください。
イノベーション会計はすべての企業に役立つ("Innovation Accounting is for Everyone")
2024年4月23日
ダン・トマ氏
イノベーション会計はすべての企業に役立つ(ダン・トマ氏が"OUTCOME社ウェブサイト"に掲載したブログ記事を、本人の許可を得て翻訳、掲載しています)

かなり長い間、私は「イノベーション会計」、すなわちイノベーションを定量化するという業務活動は、自社のイノベーションエコシステムの成熟度の高い企業だけに当てはまるものであると考えていた。イノベーション会計とは、イノベーションプロセスや事業アイデアのライフサイクルを管理するフレームワーク、あるいは年間に大量の事業アイデアが創出されるといった基本的な体制が整った段階で初めて取り組むべき課題である、というのが当時の私の見解であった。
私がそのように確信していたのは実証結果に基づく証拠の裏付けがあったからだ。私たちが約400社のグローバル企業を対象に実施したイノベーション成熟度の分析調査の結果、0から4のスケールで成熟度レベルがおおよそ3.08付近に位置する企業が、イノベーション測定の必要性が最も高いことが明らかになった。この相関関係は理にかなっているように思われる。というのも、私たちの著書『イノベーション・アカウンティング』では、20を超える相互に関連する指標で構成される包括的なシステムを提示しており、その運用には一定のガバナンス体制の整備が前提となっているからである。
しかし最近になって、私は自分のスタンスを見直した。イノベーションの測定を検討するためには、企業が基本的なレベルのガバナンスを整備済みであることが必要という考えは依然として変わらないが、改めて振り返ると、「イノベーション会計はイノベーション成熟度の高い企業だけが悩む贅沢な問題だ」という私の考えは間違っていたかもしれないと気づいた。
イノベーション会計は、イノベーションの成熟度に関わらず、あらゆる企業にとって重要である。違いは、各企業が自社の成熟度に応じて監視する具体的な指標と、それらの指標を追跡する理由にある。
以下に、企業のイノベーション成熟度に応じて追跡を検討すべき指標をいくつかご紹介したい。また、これらの指標を追跡する意義についても解説する。
自社が「初心者レベル」、すなわちイノベーションの取り組みを始めたばかりの段階にあると認識している場合、おそらくガバナンス体制が未整備であり、社内イノベーションの経験も乏しい可能性が高い。そのような状況においては、以下のイノベーション会計指標の活用を検討することが望ましい。
追跡する指標:
- イノベーションファネル内の事業アイデアの数
- イノベーションファネルの各段階における事業アイデアの数
- イノベーションファネルのある段階から次の段階に進んだ事業アイデアの数
イノベーション会計を使用する理由:
- イノベーションの社内定着状況の把握
- イノベーション投資に対する会社の興味度合いの確認
- 社内におけるイノベーション実現の証明
しかし、もし貴社がイノベーション成熟度スケールの「中級レベル」にあると考えている場合、つまり、ガバナンスはある程度整備されているものの、イノベーションシステムの一部が欠如しているため、まだ十分には発展していないと考えている場合、そして革新的なアイデアへの投資は行っているものの、まだ大規模なイノベーション(つまり、数字に頼った活動)には至っていないと考えている場合は、以下のイノベーション会計指標の追跡を検討してみてほしい。
追跡する指標:
- イノベーションの種類別(コア、隣接、変革)のファネル内の事業アイデア数
- イノベーションファネルの各段階の適合率
- イノベーションファネル全体の推定価値
- 立ち上げ中の社内ベンチャー/事業アイデアあたりの平均推定価値
上述の初心者レベル企業におけるイノベーション会計の導入意義に加えた、さらなるイノベーション会計の活用目的:
- 自社が一般的に支持しているイノベーションの傾向の把握
- ガバナンスシステムの機能状況の確認
- 不足しているスキルや文化的要素の特定
- ガバナンスシステムの改善方法の把握
- イノベーション投資の可能性に関する経営幹部への証明
最後に、イノベーション成熟度において「上級レベル」または「先進レベル」に達している企業に所属しているという幸運な状況の場合、すなわち、完全に機能するイノベーションシステムを備え、数字を重視したアプローチを実践し、イノベーションを成長の原動力として長年活用してきた企業においては、以下の指標の追跡を検討するとよいだろう。
追跡する指標:
- 新製品活力指数
- イノベーション投資効率
- ポートフォリオ配分
- 投資配分
- イノベーションコスト
- 失敗コスト
- ファネル平均コンバージョン率
- 各事業アイデアの平均存続時間(または市場投入までの平均時間)
上述の初心者レベルや中級レベル企業におけるイノベーション会計の導入意義に加えた、さらなるイノベーション会計の活用目的:
- イノベーションが自社の事業成長にどの程度貢献しているかの確認
- イノベーションが自社にとって継続的に維持可能な投資であるかの確認
- イノベーションによる自社の破壊的変化への耐性の検証
- イノベーション会計システムのデータによる投資目標の設定および必要予算の算定
- イノベーション会計システムのデータによる戦略の妥当性の検証
お分かりの通り、イノベーションの測定は、今日までは無かったイノベーション会計システムが、明日になったら突然導入されているといった具合に、スイッチのオンオフで一瞬で実現できるものではない。最も基本的なニーズに応える最も基本的な指標から始まり、やがては最も複雑な指標に至る、という長い道のりの旅路なのだ。
イノベーションを測定する能力は、イノベーション測定の必要性およびイノベーションを管理する能力とともに進化していくものである。言い換えれば、イノベーション会計は、現時点でのイノベーション管理における自社の成熟度や専門性の程度にかかわらず、あらゆる企業において活用可能ということだ。
したがって、イノベーションの測定は「悟りを開いたレベル」に達するまで後回しにしてよいものだと考えて、自分を欺いてはならない。今すぐに取り組みを開始し、基本から学び始めるべきである。そして経験を重ねる中で、より複雑な指標を取り入れ、それらをイノベーションの実践においてより賢く活用する方法を見出すことによって、継続的にレベルアップを図るべきである。
中国の古い諺に曰く、「木を植えるのに最良の時期は二十年前であり、次に良い時期は今日である」。
本ブログ記事は、もともとイノベーション・アカウンティングのブログに掲載されたものです。
いかがでしたでしょうか。弊社では、ダン・トマ氏が欧州企業向けに導入支援を進めているイノベーション・システムを日本企業にも普及させるべく活動しております。ご興味の方は是非お問い合わせください
次回のブログは「企業イノベーション部門の衰退:それがなぜ理にかなっているのか、そしてイノベーションと戦略を再び結びつける方法("The Decline of Corporate Innovation Arms: Why It Makes Sense and How to Reconnect Innovation with Strategy")」という、イノベーションの取り組みが十分に成果を上げていない企業におけるイノベーションへの取り組みの見直し状況や具体的な施策についてのお話です。
WRITER

- 渡邊 哲(わたなべ さとる)
-
株式会社マキシマイズ シニアパートナー
Japan Society of Norithern California日本事務所代表
早稲田大学 非常勤講師
東京大学工学部卒。米国Yale大学院修了。海外の有力ITやイノベーション手法の日本導入を専門とする。特に海外ベンチャー企業と日本の大手企業や団体との連携による新規事業創出に強みを持つ。三菱商事、シリコンバレーでのベンチャー投資業務等を経て現職。ビジネスモデル・ナビゲーター手法の啓蒙活動をはじめ、日本のイノベーションを促進するための各種事業を展開中。
「アントレプレナーの教科書」「ビジネスモデル・ナビゲーター」「イノベーションの攻略書」「DXナビゲーター」「イノベーション・アカウンティング」を共訳/監訳。