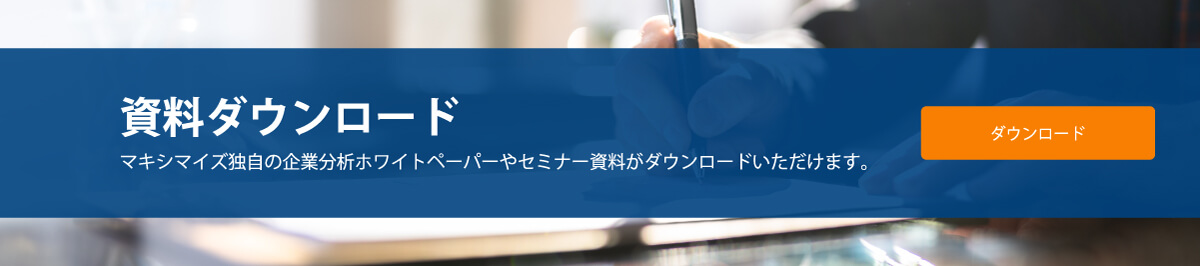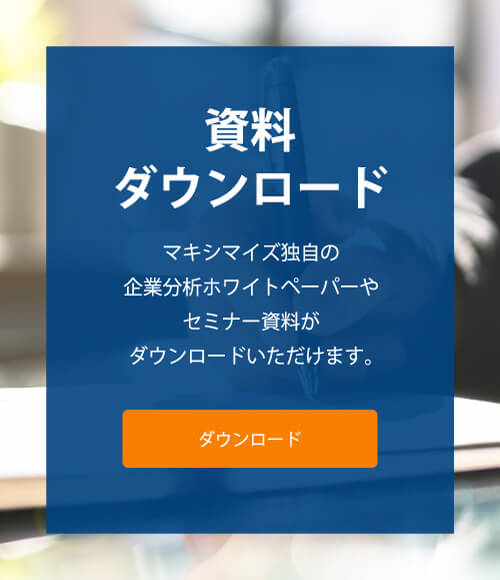今後の道筋を管理する: 循環型経済のためのビジネスモデルの開発に関する6つの洞察("Managing the path forward: Six insights on developing business models for the circular economy")
みなさんこんにちは。マキシマイズの渡邊です。今回も、既存事業を持つ大企業がシリコンバレーのスタートアップに負けない画期的な新規事業を創造するために、インダストリー4.0の一環としてスイスで開発された手法である『ビジネスモデル・ナビゲーター』開発元BMI Lab社のブログを皆さんにご紹介します(※BMIとはBusiness Model Innovation:ビジネスモデル・イノベーションの略です)。
今回のブログは「今後の道筋を管理する: 循環型経済のためのビジネスモデルの開発に関する6つの洞察("Managing the path forward: Six insights on developing business models for the circular economy")」という、サーキュラーエコノミーのビジネスモデル開発を進める際に念頭におくべき各種の原則についてのお話しです。では本文をお楽しみください。
今後の道筋を管理する: 循環型経済のためのビジネスモデルの開発に関する6つの洞察("Managing the path forward: Six insights on developing business models for the circular economy")
2024年5月29日
今後の道筋を管理する: 循環型経済のためのビジネスモデルの開発に関する6つの洞察(BMI Lab社ウェブサイトのブログ記事を、同社の許可を得て翻訳、掲載しています)
循環型経済、持続可能性
循環型社会への道のりにある紆余曲折を恐れずに:移行を管理し、予測する方法
循環型経済(CE)は、新たなビジネスモデルを通じて年間6,500億ユーロの市場成長が見込まれるなど、注目を集めており、各業界への影響もますます大きくなっている。過去2年間にわたり、我々はサーキュラー・ナビゲーター・アプローチ(HBR、2021年)を用いて、特に鉱業、自動車、ヘルスケア分野の企業と連携し、循環型経済に向けたビジネスモデル開発に関する貴重な知見を得てきた。
本ブログ記事では、企業が循環型経済へ移行する際に役立つ洞察を提供する。
学び①:循環型経済(CE)を包括的な変革として認識する
循環型経済への参入にあたっては、各プロジェクトや取り組みを、企業全体に浸透させる広範な変革の一部として捉える必要がある。このためには、経営トップの全面的なコミットメントと、初期段階から全社的な積極参加が不可欠である。これにより、持続可能な取り組みに向けた包括的かつ統一されたアプローチを確立することができる。たとえば、全社的な循環型経済(CE)キャンペーン、イントレプレナーシップ(社内起業家精神)プログラム、あるいはCEラーニングジャーニーの実施によって実現可能である。
なぜこれが重要なのか?
個別プロジェクトから着手し、学びを得て初期成果を示すことは理にかなっている。しかし、トップマネジメントによる十分な理解と支援がなければ、循環型プロジェクトは成功しない。なぜなら、循環型の変革は設計、調達、販売をはじめとする企業全体に影響を及ぼすからである。
学び②:循環型経済(CE)をイノベーションの課題として捉える
CE導入をイノベーション課題として位置付けることが、成功への道を切り開く鍵である。これには、トップダウンの方向性指導の徹底、体系的なステージ/ゲートプロセスの導入、早期段階でのパイロット実施が含まれる。顧客からのフィードバックを継続的に統合することは不可欠であり、これによりCEの取り組みが組織の目標と整合しつつ、市場の変化する需要にも的確に対応できるようになる。サーキュラー・ナビゲーターのような体系的アプローチは、新たなビジネス機会の発見と開発に貢献する。
なぜこれが重要なのか?
循環型経済は、エコシステム内の多くのパートナーとの協力と、バリューチェーン全体を通した複雑な変革を必要とする。このため、多大な労力と調整が求められ、結果として顧客ニーズを見失ったソリューションに至ることも少なくない。実際の付加価値と強い顧客需要が伴わなければ、循環型経済は成功し得ない。
これをイノベーション課題として位置付けることで、イノベーションマネジメントにおいて確立された既存のツールやプロセスを活用でき、取り組みを円滑に進めることができる。
学び③: コスト削減の特定から着手する
循環型経済への移行は、返品された製品の有効活用や生産廃棄物の最小化といった、即時に実現可能なコスト削減機会の特定から始めるべきである。移行を初期段階から経済的に魅力あるものとすることで、前向きかつ持続可能な成長軌道を築くことができる。循環型パターンカードは、こうした潜在的なコスト削減領域の特定に役立つ。
なぜこれが重要なのか?
循環型プロジェクトの初期段階では、変革の機会が多岐にわたるため、資金が限られていたり、リソースを分散して活用せざるを得ない場合が多い。とはいえ、本気で取り組むためには、早期に目に見える成果を挙げることが望ましい。ただし、こうした成果は一見容易に思えることが多い(たとえば、製品の返品をより有効に活用することは、それほど複雑には思えないかもしれない)が、実際にはプロセス上や能力面で多くのハードルに直面することが少なくない点に留意すべきである。
学び④: 長期的な利益を見据えてKPIを調整する
短期的な利益は一時的な収益増加をもたらす可能性があるものの、本質的にはCE導入による長期的な大きなメリットを理解し、強調することが重要である。製品や材料の再利用による売上増加は、持続的な事業の転換を意味しており、こうした広い意味での環境目標を反映し優先するためには、財務上の主要業績指標(KPI)を一部変更する必要がある。
なぜこれが重要なのか?
サステナブルな製品として製品設計を見直すことで、再利用や、フリート管理サービスへの利用が実現する可能性があるが、このようなビジネスは当初の利益率が低くなる場合がある。一方で企業の主な収益モデルが製品販売である場合、典型的な成功指標(KPI)は製品の利益率である。循環型経済においてこのような従来型の指標を適用すると、新規プロジェクトを早期に頓挫させてしまうことになりかねない。しかしながら、ひとつの製品を複数回にわたり販売、レンタルし、あるいは再生品を製造することで、製品のライフサイクル全体でみれば、大幅に高い収益と利益を生み出す可能性がある。
学び⑤: サービスとしてのモデル(アズ・ア・サービスのモデル)を採用する
As-a-Serviceモデルを導入することで、多数の個数の製品群を主体的な管理、使用状況と回収率の最適化を実現しやすくなる。また、中核サービスにとどまらず、補完的なサービスを導入することで、循環型プロセスにさらなる付加価値を加え、収益性を向上できる可能性がある。これらの新たなサービスを体系的に開発するためのツールが、ザンクト・ガレンのEquipment-as-a-Service Navigatorである。
なぜこれが重要なのか?
As-a-Serviceモデルは、サステナビリティおよび顧客ニーズと企業のインセンティブをうまく一致させる。従来型のリニアなモデルでは製品を一定期間後に陳腐化させることで追加の製品売上が促進されるが、As-a-Serviceモデルでは、製品を長寿命化することで、同一製品に対してより長い期間にわたって利用料が発生するため、企業により大きな利益がもたらされる。同様の理由から製品の修理性と保守性を高めることも利益の増加につながる。
学び⑥: 販売アプローチとインセンティブをカスタマイズする
循環型経済においては、販売戦略とKPIのカスタマイズの必要性を認識することが不可欠である。サステナビリティの取り組みを効果的に推進するためには、企業は循環型経済の目標に整合したインセンティブを策定する必要がある。そのためには、従来のアプローチから脱却し、循環型経済の考え方に即した営業チームを育成することが求められる。
循環型経済の導入初期段階において、企業は専門の営業チームを配置することで大きなメリットを得ることができる。これらのチームは、循環型ソリューションの推進、市場投入プロセスの加速、そして循環型経済の早期統合段階においてサステナビリティを中心に据えるための専門知識と熱意をもたらす。
なぜこれが重要なのか?
営業チームは現状の業務に長けており、彼らを取り巻くシステム全体も成果の最適化に向けて構築されている。循環型ソリューションやオファリングに関しては、提供内容に大幅な変化が生じるのが一般的である。例えば、製品ではなくサービス、購入ではなくレンタル、交渉材料として使用すべきではない買戻しオプションの提供などが挙げられる。さらに、購買センター、あるいは購買決定に影響を与える役割についても、従来とは大きく異なる場合がある。そのため、企業が販売インセンティブを適切に調整せず、営業担当者への適切なトレーニングも行わずに、新たなソリューションを既存の営業チームに単に押し付けた場合、往々にして苦戦を強いられることになる。
循環型の未来を形作る
循環型経済への移行は、包括的なアプローチ、粘り強い取り組み、そして企業内での明確なKPI設定を要する包括的な道のりである。多くの企業はすでにこの道を歩み始め、貴重な学びを得ている。われわれは、こうした学びや洞察を共有することこそが、より多くの企業に最初の一歩を踏み出させる鍵であると考えている。
いかがでしたでしょうか。弊社では、ビジネスモデル・ナビゲーターを日本企業にも普及させるべく、ワークショップやプロジェクト支援など様々な支援サービスを提供しております。ご興味の方は是非お問い合わせください。
次回からは、書籍『イノベーションの攻略書(原題:The Corporate Startup)』や『The Innovation Accounting』の著者であるダン・トマ氏のブログ記事をご紹介します。
WRITER

- 渡邊 哲(わたなべ さとる)
-
株式会社マキシマイズ シニアパートナー
Japan Society of Norithern California日本事務所代表
早稲田大学 非常勤講師
東京大学工学部卒。米国Yale大学院修了。海外の有力ITやイノベーション手法の日本導入を専門とする。特に海外ベンチャー企業と日本の大手企業や団体との連携による新規事業創出に強みを持つ。三菱商事、シリコンバレーでのベンチャー投資業務等を経て現職。ビジネスモデル・ナビゲーター手法の啓蒙活動をはじめ、日本のイノベーションを促進するための各種事業を展開中。
「アントレプレナーの教科書」「ビジネスモデル・ナビゲーター」「イノベーションの攻略書」「DXナビゲーター」「イノベーション・アカウンティング」を共訳/監訳。